

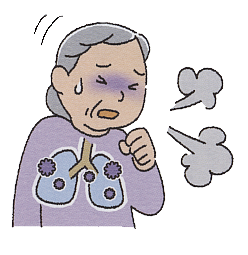
肺炎で亡くなる人の約98%は、65歳以上の人となっており、そこには加齢による免疫力の低下が関係しています。

肺炎は、肺に細菌やウイルスなどが感染して炎症が起こることで発症します。
○細菌性肺炎=肺炎球菌による感染例が多い。
○ウイルス性肺炎=インフルエンザや新型コロナ、RSウイルスなど。
○誤嚥性肺炎=食べ物や唾液と一緒に細菌が肺に入る。
肺炎の症状としては、38で以上の発熱、激しいせき、痰、呼吸困難、胸痛などが代表的です。
【加齢による免疫力の低下】 加齢とともに細菌やウイルスに対する免疫力は低下するため、肺炎の発症リスクとともに、重症化リスクも高くなります。
加齢に加え、なんらかの持病がある場合や、生活習慣の乱れによっても免疫力が低卜します。
【いつもと様子が違う】
65歳以上の方の場合、先述した肺炎の代表的な症状がないのに、「呼吸が浅く速い」「倦怠感が強い」「食欲がわかない」「意識障害がある」といった症状が見られることがあります。
こうした状態から肺炎が急激に悪化するケースもあるので、普段と違う様子が見られたら軽視せずに、かかりつけ医に相談しましよう。
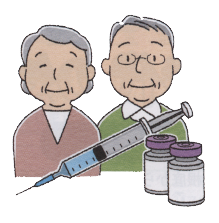 65歳以卜の方の肺炎予防には、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンの接種が、重症化リスクを抑えるために重要になります。
65歳以卜の方の肺炎予防には、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンの接種が、重症化リスクを抑えるために重要になります。
【肺炎球菌ワクチン】 肺炎球菌ワクチンは、「65歳」の方が定期接種の対象となっていて、公費(一部自己負担あり)で接種が受けられます。
※対象年齢以外の方は、任意接種となります。 成人用の肺炎球菌ワクチンは、重症化した肺炎球菌感染症の4~5割を占めているとされ、23種類の血清型の肺炎球菌に対応しています。
効果の持続期問は、健康な人で5年以上とされています。
【インフルエンザワクチン】 インフルエンザワクチンは、 「65歳以L」の方が定期接種の対象となっています。 インフルエンザウイルスに感染すると、気道の表面の細胞が破壊され、肺炎球菌などの細菌が肺に定着しやすくなり、肺炎を重症化させることがわかってきました。
インフルエンザの合併症として肺炎が起こると、ケースによっては死亡につながる恐れがあります。
肺炎になった高齢者の約70%が、誤嚥性肺炎と言われています。
誤嚥性肺炎の発症には、嚥下障害が関わっていることが多くあります。
65歳以上の方で、次のようなことが頻繁に起こるようであれば注意が必要です。
①飲み物でむせる。
②寝ているときにむせて目覚める。
③食事をすると声が枯れる(気道にある声帯に飲食物や唾液が入り込むため)。
また、誤嚥したときに細菌やウイルスを肺に入れないために、起床時や食事のあと、そして就寝前は、
うがいや歯を磨いて口胱内を清潔にすることが、誤嚥性肺炎の予防につながります。
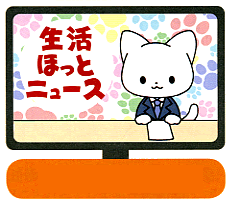 生活ほっとニュース~「社会的処方」
生活ほっとニュース~「社会的処方」
「社会的処方社(social prescribing)」は、1980年代のイギリスで生まれた活動です。
その後、「社会的処方計画を受けた患者の80%が救急外来、外来診察、入院の使用を減らし た」といった報告もありました。
社会的処方では、医師が患者の治療を行なうときに、その人が抱いている孤独感や社会的な孤立状態に着目します。
具体的には、GPという一般医・家庭医が、治療と同時にこうした問題への対応が必要と判断したら、リンクワーカーと呼ばれる方を紹介します。
 リンクワーカーは医療従事者ではありませんが、専門知識を使って、社会的に孤立している患者を、地域のコミュニティヘとつなげる役割を担っています これにより、コミュニティのなかで患者自身の持つ力が引き出され、幸福感や満足感といっ たものを取り戻していくことが期待できます。
リンクワーカーは医療従事者ではありませんが、専門知識を使って、社会的に孤立している患者を、地域のコミュニティヘとつなげる役割を担っています これにより、コミュニティのなかで患者自身の持つ力が引き出され、幸福感や満足感といっ たものを取り戻していくことが期待できます。
高齢化社会を迎えて孤立が社会問題となっている日本でも、かかりつけ医制度や地域医療ケ アを通じて、社会的処方の取り組みが始まっています。 例えば、かかりつけ医と医療保険の運営団体が協働して、地域社会の活動とつながりながら 社会生活の課題にアプローチするモデル事業が、複数の都道府県において行なわれています。
資料提供:メディカルライフ教育出版